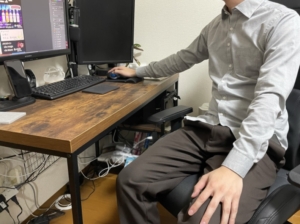2023年10月、埼玉県で提出された「子ども留守番禁止」条例案は、子どもの安全を守るという意図とは裏腹に、多くの家庭から現実離れしているとの批判を受け、わずか6日後に撤回されました。 [1] 本条例案を通じて浮き彫りになったのは、共働きやひとり親世帯が増える現代社会において、育児支援の現場と制度設計の間にある深い溝です。
さらに、海外の制度を参考にしたとされる内容は、日本の社会的背景との違いを無視していたとも指摘されました。この記事では、埼玉県の条例案の経緯と問題点を整理しつつ、日本と海外における「子どもの留守番」事情の違いについて深掘りしていきたいと思います。
「子どもだけで留守番=虐待?」埼玉の“留守番禁止条例”に10万人超の反対署名
現実とかけ離れた子育て支援
埼玉県の自民党県議団が2023年10月4日に提出した「留守番禁止条例案」(正式には埼玉県虐待禁止条例改正案)は、小学3年生以下の子どもを一人にすることを虐待とみなす内容でしたが、多くの批判を受け、オンライン署名は10万人を超え、[2] 条例案は10月10日に撤回されました。
共働き世帯やワンオペ育児が増える中、親が常に子どもにつくのは現実的でなく、育児環境を考慮していないとの声が上がりました。特に、一人親家庭や母親に育児負担が偏る現状を踏まえ、条例制定よりも学童保育の拡充や働き方改革などの支援が先決だという意見が多く上がりました。
- 共働きや一人親世帯が多い現代の家庭事情を考慮していなかった
- 子どもを一人にしないための代替制度(学童・支援など)が整っていないまま規制だけを進めた
- 文化や支援制度が異なる海外の例(アメリカなど)という前提を無視して導入しようとした
- スクールバスやベビーシッター文化など日本にない支援体制が前提となっている海外制度を参考にした
- バス置き去り事故対策という出発点から論点がズレ、広く子育て家庭に負担を与える内容になってしまった
この条例案の問題点は、まず子どもの安全を守るという目的と、現代の家庭の実情との間に大きな乖離があった点にあるといえます。子どもを一人にしないための制度設計が不十分で、現実的な育児支援が提供されていなかったにも関わらず規制を進めようとしたことが結果として多くの反発を招きました。
また、海外の育児制度(例:アメリカの州法)を参考にしたとされるが、前提条件(保育文化・送迎支援等)が大きく異なるにも関わらず、社会制度の違いを考慮せず、海外の制度をそのまま導入しようとした点も問題視されました。
特にアメリカでは、例えばメリーランド州では8歳未満の子どもを一人にすることが禁止されており[3]、イリノイ州では14歳未満の子どもを放置することがネグレクトとされる可能性があります。[4]しかし同時に、スクールバスの普及やベビーシッター文化の定着など、日本とは異なる育児支援環境が整っているため、単純に制度を輸入することはできません。
また、本来の目的であった「バス置き去り事故防止」から論点が逸れ、子育て中の家庭に新たな負担を課す内容になってしまったことも、社会的な反発を招いた要因です。
世界各国の子どもの教育に関する条例等と子育て支援、保護者による対策など
アメリカ
- 義務教育年齢:6-18歳
- 成人年齢:州による(18~21歳)
- アルコール摂取可能年齢:21歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:18歳未満は規制あり
未成年の留守番に関する条例など
州ごとに法律が違いますが以下の二つの州にはこのような法律があります。その他の州では大人の判断に任されており、基本的には緊急時に緊急連絡が出来る成熟度や年齢(大体12歳以上)が留守番できる年齢とされています。
-メリーランド州-(8歳未満の子供を家に一人で残すことを禁止する)
-イリノイ州- (14歳未満の子供を一人にすることをネグレクトとみなす可能性がある。)
その他の州-Child Protective Services (CPS)によるガイドラインが参考にされている[3][4]
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
高校生以上で講習を受けるとベビーシッターとしてアルバイトができるようになり、13歳以下の子供と留守番できるようになる為、一般的に親が出かける際にはベビーシッターを雇うことが多くあります。また、「ビフォアースクール」「アフタースクール」と呼ばれる学童保育のような制度があり、長期休暇には、「キャンプ」と呼ばれる体験教室やスクールに通わせることもあります。送迎への対応や、高い保育料や学童保育料、キャンプ費用の節約として夫婦で勤務時間や休暇をずらしたり、それぞれリモートワークを交代で取り入れやすい社会であるため、残業があっても、家に持ち帰ることによって対応可能だと考えられます。米国には日本のような長時間の残業や、仕事帰りの付き合いを良しとする文化がない為、終業時間に帰り、家族と過ごす時間を優先することが多く、ワンオペは日本のように多くありません。
子供を一人にして違反とされた事例など
アメリカ・ジョージア州で5人の子どもを育てるシングルマザーのメリッサ・ヘンダーソンさんは、2020年5月、仕事のために14歳の娘に留守を任せた。しかし、4歳の息子が友人を見つけて一人で外に出たことを近隣住民が警察に通報し、ヘンダーソンさんは逮捕・起訴されました。[5]この事件には、「地域で子どもを育てるべきなのに、母親を追い詰める社会の矛盾」として多くの批判が寄せられました。
子育て支援制度や少子化対策など
アメリカでは税制の所得控除を除けば、児童手当制度や出産休暇・育児休暇の制度や公的な保育サービスがないながらも、民間の保育サービスが発達しており、子育て後の再雇用や子育て前後のキャリアの継続が容易であること、男性の家事参加が比較的高いといった社会経済的な環境を持つと言えます。又、アメリカは州ごとに法律が異なるので、国を挙げての少子化対策はありませんが、その割に出生率が比較的高い理由には、移民を受け入れてきた歴史が挙げられます。ヒスパニック系移民の出生率は、白人の出生率よりも高いことが分かっています。また、民間の保育サービスが充実していることも、子育てしやすい環境につながっているようです。
オーストラリア
- 義務教育年齢:6-17歳
- 成人年齢: 18歳
- アルコール摂取可能年齢:18歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:18歳未満は宿泊時規制あり
未成年の留守番に関する条例など
-Queensland―12歳未満の子供を過度な時間一人にすることを禁止しています。
-その他の州:条例はないものの、小さな子どもに留守番させる行為が危険と判断された場合、罪に問われる可能性があります。
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
オーストラリアでは、保護者はフレックスタイムや在宅勤務を活用して対応しているようです。企業は柔軟な労働環境を整えており、短時間勤務や在宅ワークを許可するケースが増えています。また、共働き世帯を支援するため、最大85%の保育料補助制度が導入され、育児休暇制度も充実しています。[6]さらに、家事・育児は夫婦で分担するのが一般的で、父親の育児休暇取得率も高く、平日の学校送迎や習い事の送り迎えは夫婦で協力し、長時間労働を避けながら家庭と仕事を両立させる工夫が見られます。職場でも、従業員が長期休暇を取得する際は短期雇用で補うなど、柔軟な対応が取られており、こうした働き方と社会全体の支援が、子どもを一人にさせない環境づくりに寄与していると言えます。
子供を一人にして違反とされた事例など
2022年、メルボルンではショッピングセンターの駐車場にて車の中に子供2名を30分間放置したとして父親が逮捕された事例があります。[7]
子育て支援制度や少子化対策など
オーストラリアでは、子育て支援が充実しており、国の助成金や医療制度を活用できます。
-メディケアという国民健康保険制度により、診察や基本的な検査が無料で受けられ、出産時の医療費も公立病院なら無料、私立でも一部負担のみで済みます。
-出産時の補助金に加え、育児休暇の援助金や家族税給付金があり、デイケアセンターに通う費用が免除されたり、祖父母が子供の面倒を見る場合にサポート費用が受領できる場合などの制度が整っています。[8]
イギリス
- 義務教育年齢:5-16歳(イングランドは18歳)
- 成人年齢: 18歳
- アルコール摂取可能年齢:16歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:18歳未満は規制あり
未成年の留守番に関する条例など
英国の法律では、12歳以下の子供を一人で通学させたり留守番させたりすること自体を違法とする規定は存在せず、英国政府の公式ガイドラインには、「12歳以下の子供を一人で出歩かせることは推奨されないが、最終的には親の判断に委ねられる」と明記されています。つまり、親としての責任を果たすために慎重に判断することが求められています。[9]
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
イギリスでは法律で子どもを一人にする明確な年齢制限はありませんが、安全が確保されない状況での留守番は犯罪とされます。そのための保護者側の対策として以下のような工夫がされています:
1. 祖父母に預けるのが一般的で、長期休暇中にローテーションを組んで孫の世話をする家庭も多い。
2. 祖父母が近くにいない場合は、ホリデークラブ(学童クラブ)を利用する。スポーツやアクティビティを提供し、費用も比較的手頃なため、多くの家庭が活用している。
3. ナニーやチャイルドマインダー、ベビーシッターなど個別ケアを選ぶ家庭もあり、コストや対応時間に応じて使い分ける。
4. 親自身が有給休暇を取ることも多く、夫婦で交代したり、家族旅行を計画したりするなどして対処している。
こうした工夫により、イギリスの親たちは子どもを一人にしない育児環境を整えています。
子供を一人にして違反とされた事例など
ある日本人家庭では、親が仕事で家を空ける際に、10歳の子供を一人で留守番させていたところ、近隣住民が心配して通報し、ソーシャルサービスが介入する事態となりました。このようなケースでは、親が子供を一人にすることのリスクを十分に理解していなかったことが問題だと言えます。一方で、別の家庭では、近隣の英国人家庭と良好な関係を築き、互いに子供を見守り合う体制を整えることで、安心して仕事に出かけることができるようになったケースもあります。これは、現地の文化に適応しながらも、自分たちの価値観を尊重する方法として成功した例であると言えます。[10]
子育て支援制度や少子化対策など
イギリスには「タームタイム・ワーク」という働き方があります。タームタイムは学期を意味し、「タームタイム・ワーク」とは、子どもの夏休みや冬休みのスケジュールに合わせて、働くことができる仕組みです。イギリスでは10人に1人がこの働き方をしているようです。また、イギリスでは医療費が無料であるため、出産や避妊治療にかかる費用、子どもの医療費も必然的に無料です。[11]
日本
- 義務教育年齢:6-15歳
- 成人年齢: 18歳
- アルコール摂取可能年齢:20歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:特に無し
未成年の留守番に関する条例など
日本では児童虐待防止法違反、保護責任者遺棄罪(刑法218条)等があるが、他の国のように留守番について細かく罰則を定めた法律はない。
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
「共働き/一人親世帯における子どものお留守番に関する調査」では
・子どもが一人で留守番することに不安を感じて「働く時間を短くした」 37.3%
・転職や在宅勤務に切り替えるなど働き方を変えた 34.0%
などの回答から、子どもが一人で過ごす時間を避けるよう、苦心している親が少なくないことが浮き彫りになりました。[12]
その一方で、学童を利用する割合が小学4年生を境に減少している点に加え、「いつまで学童を利用させたいか」という質問に対して
・小学3年生まで32.8%となり、
学童利用を辞める主な理由は
・子どもが嫌がるから(34.3%)、子どもだけでも留守番ができるようになったから(32.7%)との回答となりました。[12]
日本では2025年に予定されている「育児・介護休業法の改正」で子どもの看護休暇の対象年齢が引き上げられるなど、育児とキャリア形成の両立に向けた施策が進んでいます。ほかにも、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するためにさまざまな措置が盛り込まれる予定です。
子供を一人にして違反とされた事例など
日本では、子供を留守番させて警察沙汰になるということはほとんどありませんが、例えば、夏の暑い日に駐車場で子供を車内に放置した場合や年齢の幼い子供を長時間家に子供だけで放置した場合など、警察が介入する場合はあります。また、愛知県名古屋市で5歳と3歳の娘を、4日間連続で半日以上放置したとして父親が逮捕された、というような例のように過度に常識を逸脱した監護義務に違反した場合には逮捕されることがありますが、短時間での留守番などは家庭の判断とされている場合が多いと考えられる。[13]
子育て支援制度や少子化対策など
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
(内容)
1.「子の看護休暇」の取得事由や対象者の拡大
2.残業免除の対象者拡大
小学校就学前の子どもを養育する従業員まで対象(改正前:3歳未満)
3.育児のためのテレワーク環境整備
育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
4.育休取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大
5.介護と仕事の両立支援の強化
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
雇用環境整備等の措置
介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護のためのテレワーク導入
6.育休取得などの状況把握・数値目標設定の義務化(※次世代育成支援対策推進法)
7.「柔軟な働き方を実現するための措置等」の2つ以上の実施
8.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 [14]
フランス
- 義務教育年齢:3-16歳
- 成人年齢: 18歳
- アルコール摂取可能年齢:16歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:18歳未満規制あり
未成年の留守番に関する条例など
法律はないものの、一般的には10歳未満の子供を一人にすることは避けられるべきとされています。フランスでは子供を一人で放置することが重大な社会的、法的問題へと発展することがある為、短時間であっても、この行為は厳しい罰則を受ける可能性があり、フランスに来たばかりの家庭では、特に気を付ける必要があります。
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
フランスでは小学校の子供は10歳頃までは親が一緒に学校へ送り迎えをしなければならず、親子で電車やバスに乗って通学するのが一般的で、車を使う場合でも学校の中まで送ることが求められます。放課後になると先生が児童一人ひとりを親に引き渡し、先生が必ず保護者を確認します。共働きの家庭では、シッターさんが代わりに子供を迎えに来ることも一般的です。また、10歳未満の子供が公園に行く際、必ず親が一緒に同行し、子供たちは常に親に見守られながら遊んでいるようです。
子供を一人にして違反とされた事例など
日本人家族がフランスにて子供を15分家に置いて買い物に出掛けて帰宅したところ、隣人から警察に通報されてしまうという事例があり、フランスでは子供の留守番に関し、地域の目が行き届いていることがよくわかります。[15]
子育て支援制度や少子化対策など
ベビーシッターは公的支援として収入に応じた一部払戻制度があるため、利用率は高いそうです。フランスの代表的な子育て支援には、2子以上を養育する家庭に子どもが20歳になるまで支給される家族手当、3子以上養育する家庭への大幅な減税や年金の増額などが挙げられます。職場では勤務日や時間を自由に選択でき、育児休暇中は父母ともに賃金の80%を保障されたり、保育機関に子どもを預ける場合は、補足手当を受けたりすることもできます。また、認定保育ママやベビーシッターといった子どもの預け先が多く、待機児童問題に悩むことも少ないようです。高校生までの学費は原則的に無料で、大学も数万円程度の手続き料がかかる程度でほぼ無料で通うことができます。出産にかかる費用は無料、不妊治療の費用も43歳までは公費で賄われ、事実婚や婚外子も社会的に認められており、これらの制度が適用されます。[16]
ドイツ
- 義務教育年齢:6-15歳(一部の州では16歳まで)
- 成人年齢: 18歳
- アルコール摂取可能年齢:16歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:保護者同意書が必要な場合あり
未成年の留守番に関する条例など
法律はありませんが、子供福祉法に基づき、一般的には12歳以上の子供は短時間の留守番が可能とされており、子どもの成熟度や状況に応じて判断されます。年齢制限の法律はないものの、さまざまな機関が子どもの年齢や成長度に応じて「留守番のガイドライン」を提供しています。(下記はその一例)
・3歳までの子どもは常に監視を必要としているため、決して一人で家に残さない。
・4歳〜6歳の子どもは15〜30分間は一人でいられるようになる。ただし、これは子どもの安全が確保され、親がすぐに家に戻ることのできる場所にいる場合にのみ適用される。
・7歳頃からは、家で2時間まで一人で過ごせるようになる。
これらはあくまでも目安であり、常に子どもの発達を観察し、子ども自身が「約束を守って留守番ができる」という意思を持っていることが重要とのことです。[17]
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
近年のドイツでは共働き家庭において子どもをひとりで留守番させるケースが増え、子どもの安全をどう確保するのかが大きな課題となっています。放課後の学童保育の対象は、基本的には両親が働いている家庭の子どもたちですが、親が大学や職業訓練校に通っている場合も利用可能です。(利用料金は保護者の所得に比例し、各世帯によって異なる。)保育時間は16時までが一般的であり、ベルリンなどではフリーランス勤務者が多いこと、また会社勤めでも、子どもが小さいうちは時短勤務をしている保護者が多いことから、この時間のお迎えが可能になっていると考えられます。
子供を一人にして違反とされた事例など
在独邦人家族で、父親の勤務中、一人買い物に出た母親が知人に会い、「子どもは自宅でお留守番」していることを何気ない会話の流れで伝えたところ、それが通報されたケースもあります。また、同会社にて夫婦でたまたま同じシフト時間帯に勤務していることがわかり、子供を留守番させていることがわかれば、同僚から通報される、といったケースもあるようです。[18]
子育て支援制度や少子化対策など
ドイツでは、親が病気の子どもの看病を行うために仕事を休む権利が法的に認められており、「子の看護休暇(Kinderkrankengeld)」の制度があります。さらに子どもが病気になった場合、一般的には母親が仕事を休んで看病するケースが多いですが、この制度では両親が平等に休暇を取得できることが魅力の一つでもあるようです。さらにドイツでは、子どもの病気時に親が仕事を休むことはもちろん、テレワークや柔軟な勤務時間制度を導入している企業も多く、子どもの看病をしやすい環境が整えられています。
ニュージーランド
- 義務教育年齢:6-16歳
- 成人年齢: 20歳
- アルコール摂取可能年齢:18歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:18歳未満のみでの宿泊は不可
未成年の留守番に関する条例など
子どもの留守番規制に関してもっとも厳格な国として、ニュージーランドが挙げられます。同国では、14歳未満の子どもを自宅にひとり残して放置するのは違法であり、違反した場合、最高2000ニュージーランドドル、日本円で約18万円の罰金が科されます。[19]
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
・学童保育(Before/After School Programme)の利用
・ナニー(ベビーシッター)を雇う
・住み込みの「オーペア」制度を利用し、海外の若者に世話を頼む
・祖父母を頼る
・学校のホリデープログラム(School Holiday Programme)を利用
・親が休暇を取るなど、ニュージーランドでは14歳未満の子どもを一人にすることが違法なため、親はこれらの対策を講じながら働いています。
子供を一人にして違反とされた事例など
夫婦が9歳〜6ヶ月の合計6人の子供を家に留守番させてバーに飲みに行き、逮捕され、それぞれ$500の罰金となり、CYF団体により子供が一時保護されたケースがあります。[20]
子育て支援制度や少子化対策など
法律や制度、そして風土・雰囲気という社会システム全体が『子育て家庭』を最優先する形成になっています。また、ニュージーランドでは、全世帯数の約40%を占める子育て家族を“最優先”するという社会システム(法律・制度・風土)が、既に完成し、変化し続けています。Work minimum, Life maximum(仕事は最小化、人生は最大化)という国民性、価値観があり、子どもを放ったらかしにして仕事している人は、仕事が優秀であろうがなかろうが軽蔑される、という文化や雰囲気があるようです。2007年に導入された制度では、週最大20時間 (1日最大6時間)までは保育料が無料になり、数度の改正を経て、現在では対象年齢が3~5歳となっています。[21]
イタリア
- 義務教育年齢:6-15歳
- 成人年齢: 18歳
- アルコール摂取可能年齢:16歳
- 未成年による単独渡航や宿泊に関する規制:保護者同意書が必要な場合もある
未成年の留守番に関する条例など
イタリアでは11歳未満の子どもによる一人での留守番や登下校を含む外出は禁止されています。違反した場合の罰則も厳しく、刑法で裁かれるほどの重罪となる場合があります。また、11歳未満の子ども一人での留守番や外出だけでなく、イタリアでは14歳未満の子どもを室内・車内に放置することも「未成年者または無能力者の遺棄」となる刑法591条で禁止されています。自分で自分の世話をできない人の「監護」を怠った場合に適用されるもので、14歳未満の子どもを車の中に置き去りにしたり、家に一人で放置(留守番も含む)したりする行為なども含まれています。
条例を守るための保護者の対策方法、子育て文化など
11歳未満の子どもはひとりで外出することが法律で許されていないため、小学校の登下校や習い事、子ども同士で遊ぶ場合の送り迎えなどは保護者の義務であり、ミラノでは両親共働きやシングル家庭の送迎は、主に祖父母またはキッズシッターが担当することが多くあります。多くの祖父母は日常の送迎だけでなく、3か月間と長いイタリアの夏休み中には仕事を休めない親の代わりに孫を海や山の別荘に連れて行くなど、1か月以上面倒をみるようです。祖父母に頼れない共働きやシングル親家庭では、ベビーシッターやキッズシッターを雇うことが一般的のようです。
子供を一人にして違反とされた事例など
-2歳から7歳の4人の子どもたちだけで留守番させた2人の母親。(大審院2013年第19327号判決)
-7歳の子どもを数時間自由に外出させた父親。子どもが警察に補導された後、3時間以上連絡が取れなかった(大審院2009年第9276号判決)
-11歳の少女を夜間自宅に1人で長時間留守番させ、電話で連絡が取れなかった母親(ミラノ控訴裁判所2011年第1139号判決)
-5歳の娘をスーパーマーケットの駐車場で車内(窓を開けて換気、チャイルドシートに固定した状態)に1人で残した父親(大審院2021年第27883号判決)[22]
子育て支援制度や少子化対策など
法律上は、子どもが12歳になるまで、通算10ヶ月(父親と母親の2人分の合計)まで、無給の休暇を取得する権利が認められています。また、子どもが6歳になるまではお給料も30%が支給されることが決められています。イタリアの休暇が長い為、子供を職場へ連れて行く光景も珍しくなく、同僚はお互い様として受け止め、子供も慣れておりおとなしく宿題をする光景などが見受けられるようです。[23]
今回の埼玉の条例案から得られる教訓は、「安全のための規制」が単に禁止措置になるだけでなく、具体的な支援策とセットである必要があるという点です。保育・学童施設の拡充、子どもを見守る地域コミュニティの形成、働き方改革による家庭時間の確保など、条例と政策は同時に検討されるべきでだったと考えられます。また、海外の制度を参考にする際には、その国の社会制度・文化的背景・支援インフラを十分に分析した上で、日本に適合する形に再構成する必要があります。
「子どもの安全」を守ることは重要ですが、それは単に「禁止すること」ではなく、「支えること」とセットで成り立ちます。社会全体が家庭のリアルに目を向け、制度と実情のギャップを埋めていく取り組みこそが、真に持続可能な子育て支援につながるのではないでしょうか。
出典
[1]プレジデントウーマン2023
https://president.jp/articles/-/74784
[2]東京新聞2023
https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/work/80016/
[3] Maryland General Assembly Family Law
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=gfl§ion=5-801
[4] Find Law When Can You Leave a Child Home Alone? https://www.findlaw.com/family/parental-rights-and-liability/when-can-you-leave-a-child-home-alone-.html
[5] Frontrow 2023
https://front-row.jp/_ct/17660676
[6]Mana-Biz 2019
https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2019/08/interview-166.php
[7]Nine News 2022
https://www.9news.com.au/national/melbourne-man-charged-toddler-baby-left-car-shopping-centre/c032a584-5ca6-4f1c-b7f5-76e104a3978a
[8] JAMS.TV 2022
https://www.jams.tv/education/186826
[9]Gov. UK The law on leaving your child on their own
https://www.gov.uk/law-on-leaving-your-child-home-alone
[10]英国生活サイト2024
https://eikoku-seikatsu.com/different-common-sense/
[11]Pointblank
https://pointblankpromo.com/news/2024/9/20/birth-rate
[12] PR TImes 2024
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000051725.html
[13]読売新聞オンライン2023
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231004-OYT1T50267/
[14]厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
[15]パリ暮らしあれこれ邁進 2024
https://nizipapaparis.com/stay-home/
[16]Pointblank
https://pointblankpromo.com/news/2024/9/20/birth-rate
[17]ShingaFarm2024
https://www.shinga-farm.com/parenting/german-rules/
[18] livedoor blog
https://fumi-deidesheim-staff-higaisha.blog.jp/archives/1590023.html
[19] NewZealand government
https://www.govt.nz/browse/family-and-whanau/childcare-and-supervision/leaving-children-by-themselves/
[20]NZherald 2004
https://www.nzherald.co.nz/nz/parents-of-home-alone-children-fined-500/QTBZNWG37TRYHKDFXCG7JDQVDM/
[21] 自治体国際化フォーラム2015
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/other/pdf/7896.pdf
[22]日経Woman2024
https://woman.nikkei.com/atcl/column/22/113000074/022100004/?P=2
[23] Up to you!
https://up-to-you.me/article/1522/