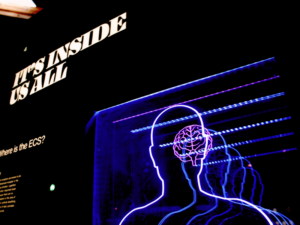「期待」から飛び出す~『氷柱の声』
第165回芥川賞候補作のひとつ『氷柱の声』。実は、読み終えるまでに数回中断し、時間がかかってしまった。どうしても泣いてしまって。同じ体験をしたことはないけれど、主人公・伊智花(いちか)の気持ちが理解できて物語にすうっと入っていくことができた。そして、痛みに泣いてしまう。
岩手の高校の美術部で絵を描く伊智花。顧問の先生に勧められ、絵画で被災地にメッセージを届ける取り組みに絵を出すことに。絵のタイトルにこめたメッセージばかり尋ねられ、違和感を覚える。伊智花が絵を描くことを止めてしまった思いと、震災で深く傷ついたけれど「家も家族も失っていないこと」への後ろめたさのようなもの。
伊智花にとっての絵を描く意味は、何かをつくる、生みだしているひとなら誰もが共感できるのではないだろうか。自分がつくりだしたものが誰かの希望になればうれしい、けれど、それが第一ではない。きっと自分が感じたこと、表現したいこと、「声」のようなものがあると思う。突き動かされる。だから、大義や後付けの感動ストーリーを乗せられてしまうのは、抵抗があるし傷つくだろう。
伊智花がほんとうに伝えたいと思っていたことが、絵を見た誰かに届いたなら。物語のこちら側で読み手である私たちも、一体となって温かい涙を流すことができる。
親のつくり出す「理想」から飛び出す~『噛み合わない会話と、ある過去について』
辻村深月さんの短編集『噛み合わない会話と、ある過去について』は、魅力的なタイトルに惹かれて手に取った。学生時代の友達、親子、教師と教え子、同級生……それぞれのシチュエーションで、見事に噛み合わない会話、ぎくしゃくした人間関係が描かれている。
完全なフィクションなので、話の展開は実際の社会や生活とは結びつかないけれど、「ああ、わかるなぁ」と思うシーンや会話が多々あった。
中でも印象的だったのは、親子関係がテーマの『ママ・はは』。主人公の友達スミちゃんは、母親ととても仲が良さそうにスマホで話しているのに、成人式のアルバム写真をきっかけに驚くような過去の話を始める。スミちゃんの母親は、かつては娘を自分の考えで振り回す横暴な親だったのだと。
「ねえ、子育てとかしつけの正解って何かな?」
「え?」
(中略)
スミちゃんが長いため息をついた。
「親にしてみたら、ある日突然思ってもみなかった通知表を渡されるようなもんだよね。親の立場は絶対で、子どもから評価されることなんてないと思ってたのに、あなたの子育てのやり方は、私にはこうだったので、大人になってからは許しません、許します、感謝しません、感謝します」
『噛み合わない会話と、ある過去について』辻村深月(講談社)より
親が厳しく、厳しさを超えてモラハラに近い子育てをしている場合。大人になって親を許せるか否かというのは根深い問題だと思う。親のポリシー、価値観をすべて引き受けなくてもよいということ。成長を経て子どもは社会人、成人として親とある意味対等になっていくということに、うなずけるのではないだろうか。
押し付けの「普通」から飛び出す~『コンビニ人間』
村田沙耶香さんの『コンビニ人間』は、読んでいてかなりきつかった。第155回芥川賞受賞作であり、話題作なのでタイトルだけは知っていたのだけれど。このきつさは、リアルの中で十分身近にありそうな話だな、と思った。
主人公の古倉恵子は、36歳のコンビニ店員。なんと18年も同じコンビニで働き続けている。この設定でまずちょっと面食らう。高校生ぐらいからコンビニでバイトをしていて、店を変えつつコンビニバイトが性に合っているんだよね、という感じの知人はいるけれど。もしこれが「1社に勤続18年です」と言えば、普通にありそうな話なのに。なぜコンビニバイトだと(私を含めて)驚いてしまうのか。それは、無意識のうちに偏見があるからだ。
恵子は子どもの頃から生きづらさを抱えている。「治る」ことを家族から望まれて。ムラ社会から弾き出されてしまうことを恐れている。その状況を救ってくれたのが、天職とも言うべきコンビニ店員の仕事だっただけ。
物語の中で、恵子は何度も「就職するか結婚したら?」と他者に迫られる。そうすることが、普通なのだと。でも、それが普通だと誰が決めたのだろう。確かに未来は見えないけれど、じゃあ誰かが決めた「普通」に従っていれば、絶対に安全安心な未来が約束されているだろうか?誰だって、不安や怖さを抱えている。「こうすれば大丈夫」なんて、今となっては誰にも言えない。何が起こるかなんてわからない。だとしたら、自分で自分の進む方向を選ぶしかないのだ。